正義とは何か?仏教と現代思想から読み解く「善悪の正体」
子どもの頃からアニメやドラマでよく耳にしてきた「正義」という言葉。
でも、大人になって改めて考えてみると、「正義って一体なんだろう?」と迷うことはありませんか?
哲学や思想の分野では、正義は長年の重要テーマです。
マイケル・サンデル教授の『これからの「正義」の話をしよう』は、まさにそれを問い直す世界的ベストセラーでした。西洋哲学では、プラトンやカント、功利主義など、さまざまな視点から正義が語られます。
では、仏教ではどう語られているのでしょうか?
仏教の視点:「正義とは自分の都合で決まる」
仏教では、正義とは**「愛憎違順(あいぞういじゅん)」**、つまり「自分の好き嫌いや都合で決まるもの」とされます。
親鸞聖人もこう語りました。
「是も非も、正も邪も、善悪も分からない」
なぜか?
それは、「時代・場所・都合」によって、正義も悪もコロコロ変わるからです。
【例①】時代によって変わる正義
昔の王政の時代、王への忠義こそが“正義”とされました。
今のように「主権在民」や「労働者の権利」なんて言ったら、不満分子として処罰の対象でした。
現代では逆ですね。むしろ権力を監視し、平等を守ることが「正しい」とされています。
このように、正義の基準は時代背景でまったく変わるのです。
【例②】場所によって変わる善悪の感覚
文化の違いでも、正義や悪のとらえ方は大きく違います。
-
日本では「平手打ち」より「拳骨」のほうが侮辱的ですが、欧米では逆。
-
「泥棒」は日本で最大級の悪口ですが、欧米では「チキン(臆病者)」のほうが侮辱とされます。
関西と関東でも言葉づかいや価値観の違いがありますよね。
【例③】自分の都合で「善悪」が決まる
自分に都合の良い人=「いい人」「正しい人」
自分を否定する人=「嫌な人」「悪い人」
こう考えてしまうのは人間の自然な心の働きです。
これを仏教では「愛憎違順」といい、「高峯岳山に異ならず(山のように大きくゆるがない)」とも表現されます。
でも、それって本当に“正義”なんでしょうか?
正当防衛や報復は仏教でどう扱われる?
仏教では、やられたらやり返すという考えは否定されます。
「やり返すことは、相手の行為を受け取ること」だと考えるからです。
仏教の理想は、「忍辱(にんにく)」という行動。
怒らず、耐え忍び、心を乱されないことが最も尊いとされます。
正義VS正義…戦争はなぜ起きるのか?
アニメ『ドラえもん』の中でこんなセリフがあります。
「どっちも、自分が正しいと思ってるよ。戦争なんてそんなもんだよ。」
(てんとう虫コミックス第1巻)
そう、**戦争は「正義VS正義」**のぶつかり合い。
リベ大・両学長の人気動画でも、「正義は人の数だけある」と紹介されています。
仏教もまさに同じことを説いています。
人間関係も「期待値」で考えてみよう
ちょっと視点を変えて、人間関係を「期待値」で見てみると…
期待値 = その人の価値 × 自分との関係の深さ(距離)
たとえば:
-
Aさん:信頼できて、よく連絡を取る → 期待値が高い
-
Bさん:能力はあるけど冷たい → 期待値は中くらい
-
Cさん:魅力はあるがほぼ関わらない → 期待値は低い
人間関係に疲れたとき、「自分はこの人にどれだけ期待してるのか?」を考えてみると少し楽になります。
最後に:仏教的な人間観
聖徳太子はこう言いました。
「我必ずしも聖に非らず 彼必ずしも愚に非らず 共にこれ凡夫のみ」
私も完璧じゃないし、相手も愚かではない。
みんな同じ「迷いの中にある存在(凡夫)」という仏教的な見方です。
正義を語る前に、自分の内側を見つめること。
それが、平和に生きるための第一歩かもしれません。
まとめ:正義とは、私たち自身の心の鏡
-
正義も悪も、時代・場所・都合で変わる
-
仏教では「自分の都合によって正義と悪が決まる」と見る
-
相手を責める前に、自分の期待・慢心を見つめよう
-
人間関係は「期待値」で考えると、少しラクになる
-
敵を作らず、心穏やかに生きる。それが“強さ”でもある
正義とは、何か。逆に悪とは何か。
正義という言葉は、子供の頃からアニメやドラマなどでよく出てきます。哲学や思想の分野で主要のテーマとして扱われることが多いです。
ハーバード大学の哲学授業の講師マイケル・サンデルの本で「これから正義の話をしよう」は世界的ベストセラーにもなりました。非常に関心の高いテーマですね。この本には、西洋の哲学者が紹介されています。
では、仏教ではどうなのかと言うことです。
結論として仏教では、「自分の都合によって決まる」といいます。これを、愛憎違順といいます。
親鸞聖人は、「是も非も、正も邪も、善悪も分からない」と言われています。なぜこう言ったのか?
その答えは、時代、場所、都合などによってコロコロ変わるからです。
例1:今より昔の長い時代では、最高道徳は、王国制度の王への忠義でした。最高の正義でした。これに反するものは、悪と言われた時代です。主権在民とか労使平等なんていうのは不満分子だからすぐに投獄になりました。今の時代は、こんなことを言ってもそうはなりませんし、否定する人もいませんよね。
例2:場所によっても、変わりますよね。分かりやすいのは、欧米と日本では相当違います。日本では、平手打ちより拳骨の方が侮辱になりますが、欧米では平手打ちが侮辱になります。日本では、「泥棒」は辛辣な悪口になりますが、欧米では「チキン(臆病者)」と言われることの方が侮辱になります。他にも、地域によってもそうですよね。関西と関東でも違いますよね。
例3:都合によっても変わりますよね。「愛憎違順することは高峯岳山に異ならず」という言葉があります。意味は、「自分に従うものは愛して近づける、自分に違うものは憎んで遠ざける」ということです。自分に従うもの、言うことを聞いてくれる人、認めてくれる人、応援してくれる人などは好きで、いい人、正しい人。逆に、自分を否定する人、認めない人、無視する人、自分のやることを止める人、自分を雑に扱う人などは嫌いで、悪い人、間違っている人。となります。
つまり、自分にとって都合のいい人かどうかとなります。そして、条件が変わるとまた評価がコロコロ変わっていきます。
雑談:仏教では正当防衛は認められるのか。仏教では「報復、復讐、仕返し、やられたらやり返す」などは嫌います。やり返すことは、受け取ることですから、受け流しなさいと教えられています。やり返すのは、相手と同じレベルになります。また、忍辱といって「怒るな、耐え忍びなさい」これが良い行いです。どんな状況でも、「軽重あっても、その行い自体には違いはない」ということです。しかし、正義ということにはならないんです。
仏教には、「正も邪も 勝手に決める 我が都合」というものがあります。
怒りとは自分が正しいという自惚れ心からきます。自分が正しい、相手が悪いという状況です。それに対して相手も同じなんですね。つまり、正義VS正義ということです。ドラえもんでも有名なフレーズです。
では、リベ大両学長の大人気動画人生論:正義について「人生論」という動画ではどうでしょうか。
結果から言えば、「正義は人の数だけある」ということです。正に、仏教そのままですよね。
動画の中の紹介でドラえもんは、「どっちも、自分が正しいと思っているよ。戦争なんてそんなもんだよ。(ドラえもん てんとう虫コミックス第一巻)」これやで、と。
まず理解してほしいことは、「人の数だけ、時代にもよるし、立場にもよる、それぞれの思惑で行動している(業界)」ということ。原因を遡っていくと自分に辿り着くんですね(智慧1/3=自因自果)。
平和に生きる最大のコツは、敵を作らない人が最強。←この辺も仏教と同じなんですね。
人は人、自分は自分、正に業界を理解することです。これをすると慢心(自惚れ心)が無くなったりします。そうすると、修羅界には、入らないんですね。
最後に、数式では、期待値の計算が近いです。得られる結果に対して確率を掛けます。以下の通りです。
ふだんの人間関係にも、「期待値」って実は当てはまるんです。たとえばこんなふうに:
期待値=各人(人の性格や行動)×自分との距離(心の近さ)の合計期待値 = 各人(人の性格や行動) × 自分との距離(心の近さ) の合計
ここでの要素を言いかえると:
・期待値:その人たちから自分がどれだけ“都合よく”満たされるかの合計(感情的な見返りや安心感など)
・各人:相手がどんな人か(優しい人、気まぐれな人、頼れる人など)
・自分との距離(確率):その人が自分に関わってくれる可能性の高さ(近い友達は高く、疎遠な人は低い)
例えばこんな感じ:
-
Aさん:とても信頼できる友人(価値高)、よく連絡を取る(距離近)
→ 高い期待値 -
Bさん:能力はあるが冷たい印象(価値そこそこ)、たまに会う程度(距離中)
→ 中くらいの期待値 -
Cさん:魅力はあるが、ほぼ関わらない(距離遠)
→ 期待値は低い
忘れてはいけないこと:
期待値は「自分の都合」ベースで測ってしまいがちですが、人との関係は確率(距離)によって大きく変わるものです。
どれだけ理想的な人でも、距離が遠ければ期待しても虚しくなります。
逆に、身近にいる人の小さな優しさのほうが、意外と大きな価値を持つことがあります。
人に期待しすぎて疲れたとき、この式を思い出すとちょっと楽になるかもしれません。
「距離」が小さければ、期待も自然と小さくなります。それは悪いことじゃなく、むしろ心のバランスを保つための大事なヒントです。
まとめ:聖徳太子はこのように言っています。「我必ずしも聖に非らず 彼必ずしも愚に非らず 共にこれ凡夫のみ」仏教では、常に己を見つめなさいといいます。

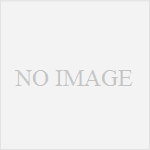
コメント