「なぜ生きる」と「どう生きる」——仏教とベクトルで読み解く人生の方向性
※この記事は個人的な解釈に基づいています。エンタメ感覚で気軽にお読みください(というか他の記事も全部そうなんですが……笑)
はじめに:生き方と生きる意味は別物
「どう生きるか」は多くの人が考えます。仕事や人間関係、健康、住む場所や食べるもの……生きるだけでも大変なことです。
一方で、「なぜ生きるか」は立ち止まって考える機会が少ないかもしれません。
仏教では、この「なぜ生きる」をこそ重視します。
「どう生きる」とは生きるための手段
衣食住、そして働くこと。スキルや資格、人間関係、健康……すべては「どう生きるか」に関わる要素です。
食べるためには働かなければならず、働くためには健康でなければならない。現代では「どう生きるか」を考えない人はいないでしょう。
しかし、それだけで満足していてよいのでしょうか?
「なぜ生きる」とは人生の目的
私たちは、なぜ生きているのでしょう?
苦しみながら、努力しながら生きるのはなぜでしょう?
必ず死ぬと分かっているのに、なぜ生きるのでしょう?
これは、**How(手段)ではなく、Why(目的)**の話です。
仏教はこの「Why」に問いを投げかけ続けてきました。
医学の例:延命の先にある問い
医学は命を延ばすためにあります。病気を治し、健康を守る。それはとても尊い営みです。
でも、ある患者が10年の苦しい闘病の末、亡くなる間際に「こんなに辛いなら、あの時死んでおけばよかった」と言ったとしたら——。
医師は戸惑います。
「この10年間は何のためだったのか?」
医学書には書かれていない「目的」の部分、つまりなぜ生きるのかという問いが、突然目の前に現れるのです。
アインシュタインの言葉とベクトルの話
アインシュタインはこんな言葉を残しています。
「科学なき宗教は妄言であり、宗教なき科学は欠陥である」
この言葉のキーワードは、「科学」と「宗教」です。
● 科学は「力の大きさ」
科学の歴史を辿れば、「より楽に、より効率的に」が軸になっています。
農業は、手作業→道具→機械→AI農業と進化してきました。これは「力点を小さくして、作用点を大きくする」——つまり「力の大きさ」を最大化する過程です。
● 宗教は「方向性」
宗教とは「家の中を示す教え」と書きます。つまり、人間が進むべき方向性を示すものです。
ベクトルで考える人生
数学で「力の大きさと方向」を表すのがベクトルです。
科学=力の大きさ
宗教=方向性
片方が欠けていると、
・科学だけでは暴走(四方八方に力が散る)
・宗教だけでは空回り(妄信に陥る)
両方が揃って初めて、人は正しく進むことができます。
仏教という「長期的な優しさ」
アインシュタインは「仏教は近代科学と共存できる唯一の宗教である」とも述べました。
仏教の方向性は、「智慧と慈悲」——長期的(論理的)なやさしさです。
これは、現代社会における科学技術の使い道を考える上で、非常に重要な視点です。
ドラえもんに学ぶ科学の使い方
のび太くんは、ドラえもんの道具を復讐や遊びに使い、結局は自分も困ってしまう……というのが定番のストーリーですよね。
これは、科学の「力の使い方」を間違えている例です。
本来、ドラえもんは「子守ロボット」であり、のび太くんの幸せのために道具を使うべき存在です。仏教では、復讐は「自損損他(じそんそんた)」として否定されます。
逆に「自利利他(じりりた)」——自分の利益が他人の幸せにもつながることが理想とされます。
まとめ:「なぜ生きる」のベクトルを持とう
「なぜ生きる」「どう生きる」は、人生のベクトルです。
-
「なぜ生きる」=方向性(目的)
-
「どう生きる」=手段(道具・技術・スキル)
どちらか一方だけでは人生はうまく進みません。
方向性が定まれば、どんなにゆっくりでも、きっと目的地には近づけます。
自分だけでなく他人の幸せも意識しながら、自分なりの人生の「ベクトル」を描いていきましょう。
仏教では、「なぜ生きる」 「どう生きる」
の違いを鮮明に説明しています。個人的解釈なのでエンタメ程度に読んでください(というか他の記事も全部そうなんですが、、、)。
仏教では、「どう生きる」よりも「なぜ生きる」の方が重要視されます。
どう生きるを考えない人はいないですよね。基本になるのは衣食住です。生きること自体が大変なことです。食一つとってみても日本ではあまり餓死するという方は少ないですけど、世界を見渡せば食べられず栄養失調になって病気になり亡くなる方がいます。食べることは生きることなんて言います。では、食べるためには働かないといけません。働かざる者食うべからずなんて言葉もありますね。働くためには健康や人間関係も良好でないといけません。仕事内容によってはスキルや資格が必要になります。これらを手に入れることで生きやすくなり「どう生きる」ということです。
では、なぜ生きるとは何でしょうか。一生懸命どう生きるで手に入れて生きているのは、なぜなのか?ということがなぜ生きるということです。How手段とWhy目的ですね。なんで生きているのか、必ず死ぬのになぜ生きているのか。苦しくて頑張って生きているのか。生きなきゃいけないのか、生きる意味は何なのか?ということです。
「目的は一切の手段に優先する」「目的の軽重は手段の軽重に決する」
例:医学の目的は延命するためです。少しでも長く健康的に生きるために病気や怪我を治すことが医学の使命ということになりますが、命が尊いから育み医学はまた尊いということで医者はとよんだり看護師のことを白衣の天使と呼んだりします。ある患者が病気にかかり10年の辛い闘病の末亡くなった。最後の言葉が「こんな辛いならあの時死んどけばよかった」と言われたらアイデンティティが揺らぐ医者は多いそうです。この治療は何だったのか。命を延ばすことはできますが何のために延ばしたのかは医学書には書いていないので患者本人のWhyの問題になります。医学だけではありません。政治、経済、科学、人間の一切の営みは健やかに長く生きるためにあるということです。そうやって生かすのは何故なのかを問題提起したのがブッタです。
ここで個人的解釈に必要になってくるのは、
アインシュタインの言葉に「科学なき宗教は妄言であり、宗教なき科学は欠陥である」という言葉があります。これはどういう意味か、キーワードになるのは「科学」「宗教」の2つです。
例:農業の歴史として、まず森で食べられるものを発見しました。それを近くに持ってくることはできないか→畑などができました。初めは手で畑を耕していました。もっと楽にできないか→道具を使うようになりました。もっと楽にできないか→機械を使うようになりました。もっと楽にできないか→現代では、AI農業が進められています。これから「科学」は何を意味するのか、「力の大きさ」「論理力(因果関係)」です。力点、支点、作用点がありますよね。力点を小さくして作用点を大きくすることが科学の役目です。
一方で、「宗教」とは何か。宗教は家の中を示す教えと書きます。つまり、「方向性」です。
数学で、「力の大きさ」と「方向性」と言えば、ベクトルですよね。「科学なき宗教は妄言である」は可視化すると点のようなものですね、「宗教なき科学は欠陥である」は可視化すると四方八方に散り乱れていることになりますね。ですので、ベクトルでは片方欠けてもダメなんです。両方必要ということです。
ですので、科学が発達すれば力が大きくなるのでますます方向性というものが大事になりますね。正しい宗教というものが必要になります。が、問題はその宗教の方向性ですね。宗教は沢山あります。アインシュタインは、「仏教は近代科学と共存できる唯一の宗教である」と言っています。仏教の方向性は、智慧と慈悲、つまり論理的な優しさです。
科学を何に使うのか、どこに使うのか。
例えば、代表的な科学の使い方にドラえもんのアニメが参考になると思います。
定番の流れは、のび太くんがジャイアンにいじめられてドラえもんに泣きついて道具を出してもらって仕返しをするが結局自分も損をするというのが王道ですよね。この場合、のび太くんは道具の使い道を間違っているんですよね。本来、ドラえもんは子守ロボットです。ドラえもんの道具はのび太くんの幸せを目的に使う必要があります。ドラえもんは教えずのび太くんが自分で気づいて欲しいと願っているんですが上手くいかないきません。使い方が間違っていますよね。仏教では、復讐は一切認めません。自損損他といい、他人の不幸が自分の不幸ということです。この逆が自利利他です。のび太くんは他人の不幸ではなく他人の幸せのために道具の方向性を考えて使わなければいけなんです。そのように使っていればジャイアンもいじめたりしないんですけどね。
まとめ
なぜ生きる、どう生きるは数学で言えばベクトルのようなものです。どちらも厳かにしてはいけません。方向性を定め、後は道具であったり自分の好きなスキルなどを磨けばいいですよね。自利利他の精神を心掛けるようにすれば良いと思います。人生の方向性が決まれば牛歩でも目的は達成できます。

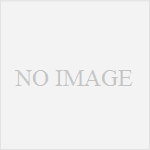
コメント