ビジネスの原点は「他者貢献」──仏教に学ぶ、成功の本質
ビジネスの本質とは何か?
それは「他者に貢献すること」です。
仏教ではこの考え方を「自利利他(じりりた)」といいます。
つまり、他人の利益がそのまま自分の利益につながるという意味です。簡単に言えばwin-winです。
反対に、
-
自損損他(じそんそんた):自分も損をして他人も損をする
-
我利我利亡者(がりがりもうじゃ):自分の利益しか考えない人
このような在り方では、ビジネスも人生もうまくいきません。
【昔話】ビジネスの原点を示す一人の男の物語
昔々、ある男がいました。
彼は土地も持たず、狩りも得意でなく、「人に雇ってもらうしかない」と考えて旅に出ました。
ある日、内陸の村に立ち寄ると、その村では塩がなくて人々が困っている。
「かわいそうだ」と思ったものの、自分には何もできず通り過ぎます。
さらに旅を続けると、今度は海沿いの村に辿り着きます。
そこでは逆に、塩は豊富だけど米が不作で人々は餓えに苦しんでいました。
そのとき、彼はふと思いつきます。
「内陸には米があるが塩がない。海沿いには塩があるが米がない。
お互いに交換すれば、どちらも助かるのではないか?」
彼は両方の村に話を持ちかけ、流通を作りました。
結果、両方の村は救われ、男自身も感謝され豊かになったのです。
この物語が示す通り、
「人の苦しみをなんとかしたい」という思いから、ビジネスは始まるのです。
他人の悩みに敏感な人が、成功する人
「自分さえ儲かればいい」「自分が得すればいい」──
このような考えでは、長期的には信頼もお金も得られません。
ビジネスに向いているのは、こういう人です:
-
周囲が何に困っているかに敏感
-
どうしたら喜んでもらえるかを常に考えている
-
「与えること」に喜びを感じる
仏教の「自利利他」は、まず他人を儲けさせる、認めることから始まります。
そうすれば、自分にも必ず幸せが返ってくるのです。
「地獄」と「極楽」の違いは、心の在り方だけ
仏教にはこんな教えがあります。
ある男が地獄と極楽を見物に行きました。
まず地獄に行くと、住人たちはみな痩せ衰え、苦しそう。
しかし、よく見ると目の前には山ほどのご馳走が並んでいます。
それなのに誰も食べられない。その理由は──
食事用の箸が2〜3メートルもある!
自分で食べようとしても、口まで運ぶ前に落ちてしまうのです。
次に男が極楽に行くと、そこでも同じように長い箸と山のようなご馳走。
しかし、住人たちは健康で笑顔にあふれ、幸せそう。
違いはただひとつ。彼らは「相手に食べさせていた」のです。
-
自分で食べようとする→地獄
-
相手に食べさせようとする→極楽
箸も料理も同じ。違うのは「心構え」だけなのです。
まとめ:与える人が、最後に豊かになる
ビジネスでも人生でも、最終的に成功するのは、
-
他人を幸せにしたいと思う人
-
他人の役に立ちたいと思う人
-
「まず与える」ことを自然にできる人
です。
仏教では「布施(ふせ)」といって、何かを与えることこそが最大の幸せだと説きます。
今、あなたの周囲に困っている人がいませんか?
それに気づき、何かしようと思える心が、ビジネスの原点であり、人生の極楽への入り口なのです。
ビジネスの原点は他者貢献である。
他者貢献は、仏教では自利利他に該当します。その逆は、自損損他や我利我利亡者と言います。
- 自利利他:他人の利益が、そのまま自分の利益になるということです。
- 自損損他:他人の損が、そのまま自分の損になるということです。
- 我利我利亡者:自分の利益ばかり、自分さえ良ければいいと考えているということです。
ビジネスの始まりはどのような話だったのか。このような話があります。
昔あるところに、一人の男がいました。その男が耕作する土地も無く狩猟も下手で、「生活していくためには人に雇ってもらわないといけない」と思って旅に出ました。旅の途中で内陸の村に立ち寄りました。その村は塩が足りなくて大変苦しんでいた。塩は生活の必需品ですから村の人たちは困り果てていた。その男は「気の毒だな、かわいそうだな」と思ったんですけど何もすることができずその村を去って行きました。しばらく旅を続けていくと今度は海沿いの村に立ち寄ったんですね。この村は塩には困らないんですけど米が不作で苦しんでいます。米がないと餓死してしまうにので苦しんでいます。この男は、その村を何とかして助けてあげたいという気持ちがありずっと悩んでいた時に、ハッと思いつきました。「内陸の村には米はあるが塩がない、海沿いの村には塩はあるが米がないということは互いに持っていけば助かるんじゃないか」ということで2つの村に掛け合い流通を考えたところ、この二つの悩みは解消し2つの村は幸せになり、そして二つの村の架け橋に尽力したこの男も感謝されまた得もしたという話です。そもそも原点を遡っていくとこの男に、この苦しみをどうにかしてやろうという気持ちがなければ解決しなかった。
ビジネスの原点はこれなんです。
ですから、相手の苦しみに鈍感であるとか他人を幸せにしたいという気持ちがない人にビジネスは向いてないんです。まず、周囲の人が何を求めているかどんなことに苦しんでいるか何をしたら喜んでもらえるのか、敏感に察知できる人じゃないとビジネスはできないんですね。そしてこれを何とかしたいと考えられる人じゃないとできないんですね。
逆に、まず自分が、もらうことを考えている人は成功しないんですね。仏教では、我利我利亡者と言います。「自分さえ良ければ、他人はどうなってもいい」というものです。
儲けたいとか認めてられたいとか思う前に、まず自分が相手を儲けさせることや認めることです。「与えることが先です。そうすると自分も必ず恵まれますよ」これが仏教精神の自利利他です。他を利するままが自分も利する。
地獄と極楽
自利利他と我利我利亡者では雲泥の差ができます。
ある男が地獄の見物に行きました。地獄の罪人はみんな骨と皮のように痩せ衰えていて「あー、ろくなもの食べてないんだな。さぞ苦しいな地獄は」とこう思っていたところ、食事が始まったんですね。「地獄は一体何を食べてんだろうな」と思って食卓を見ると、テーブルにはたくさんの山ように食べ物があるんですね。ところがそこに座っている地獄の罪人たちは痩せ衰えていて少しもこれを食べれるような感じじゃないんですね。これどうしてだろうなと思ってよく見てみると何とですね、その持ってる箸がこの食べ物を取る箸が2mも3mもあるような箸なんです。だから食べようと思ってもつかむまではいいんだけどそれを口に持っていこうとした時に全部落としてしまうんですね。だから箸がとても自分の口に持っていけるような長さじゃないというこということですね。「いやー、地獄というのは大変だな」と、「まだものがないなら、我慢はできるんですけど目の前にあるのに食べるものが、それが食べれないでいやこれは辛いだろうなということで地獄というのは苦しいところだ」ということを男は認識した。その後、地獄見物が終わり今度は極楽見物に出かけた。極楽もちょうど食事時だったんですね。極楽の食卓らしく山海の珍味、たくさんのご馳走が山と積まれて美味しそうだとしかもこの住民たちはみんな肌艶よく屈強だったり体もしっかりしてて本当に栄養がよく行き届いているそういう姿だったんですね。幸せなところだなあとこのご馳走出しと地獄と違ってちゃんとした箸でたべれるんだろうなとこう思って見てみると何とですね、極楽もこの2m3mもあるような箸なんですね。男は驚きまして、「なんだそしたら地獄一緒じゃないかそしたらなんでこんなに食べられるんだろう」と思って見てみると、極楽の住人は自分で掴んでそれを相手に食べさせていたんですね。そしたらお返しとばかりにこの人も相手に食べさせてやるとだから自分で食べようとせずにとったものを相手に渡しているんですね。それを見た時に男は手を打ってそうか地獄と極楽を分けるのは「心掛けなのか」ということで感嘆したという話です。
まとめ:地獄と極楽で違うところは何もない食卓もご馳走も一緒、箸も2m3mそれも一緒、全て一緒なのになぜこうも地獄と極楽ほど別れるかというと、地獄は自分が食べることしか考えていない、自分が得することしか考えていない相手がどうであるか少しも考えない世界。それに対して極楽は、相手に与えようという心のある人たち、この心掛けの違いです。我利我利亡者なのか自利利他なのか、その違いによって他は何も変わらなくても地獄と極楽ほどに別れるんだとという話ですね。仏教では、「布施(与える)することだけを考えなさい」と言われます。その方が長期的に見て幸せが広がっていきます。

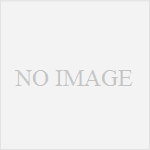
コメント