「玉の輿(たまのこし)」——
この言葉、耳にしたことがある人は多いと思います。「セレブ婚」や「逆転婚」なんて現代風の言い方もありますが、日本では昔から“庶民の夢”として語られてきた言葉です。
でも、そもそも**「玉の輿」ってどこから来た言葉なんでしょう?**
今回はその語源や歴史、そして関連する言葉について、少し深掘りしてみましょう。
■ 「玉の輿」とは?
まず意味から。
「玉の輿」とは、一般庶民の女性が、裕福な家や高貴な家に嫁ぐことを指します。現代で言えば、お金持ちや有名人、社会的地位の高い相手と結婚することを意味します。
■ 語源は「玉」+「輿」
-
「玉」=宝石のように尊いもの。転じて「高貴な人」や「立派な家柄」。
-
「輿(こし)」=昔の貴族やお姫様が乗った乗り物、いわゆる「かご」や「御輿(みこし)」。
つまり「玉の輿に乗る」とは、高貴な身分の人の乗り物に乗る=身分の高い家に嫁ぐことを、比喩で表しているのです。
■ 「玉の輿」の由来は“お玉さん”
この言葉の背景には、**江戸時代の実在の女性「桂昌院(けいしょういん)」**の存在があります。
彼女はもともと京都の八百屋の娘で、「お玉」と呼ばれていました。
やがて将軍・徳川家光の側室となり、その子・徳川綱吉が将軍に就任。
つまり、「八百屋の娘 → 将軍の母」というとんでもないシンデレラ・ストーリーを体現したわけです。
これをきっかけに「お玉が乗った輿=玉の輿」という言葉が生まれ、広まったと言われています。
■ 類語・似た表現
現代風に言い換えると、こんな言葉が近い意味を持っています。
| 表現 | 意味 |
|---|---|
| シンデレラ・ストーリー | 貧しい女性が王子様と結ばれる夢物語。 |
| セレブ婚 | 芸能人や富裕層との結婚。俗っぽい言い方ですが浸透してますね。 |
| 成り上がり婚 | 地位や収入で大きくギャップのある結婚。玉の輿に近い意味で使われます。 |
■ 対義語や皮肉な表現も
言葉は反対側を見ることで、より輪郭がはっきりします。
| 表現 | 意味 |
|---|---|
| 貧乏婚 | 経済的に苦労のある結婚。愛はあってもお金は…というケース。 |
| 身売り | 昔の社会では、生活苦から奉公や望まぬ結婚に出されることもありました。 |
| 貧乏くじを引く | 運が悪く、不本意な結果になること。結婚に限らず使われます。 |
■ まとめ
「玉の輿」という言葉は、ただの俗語ではなく、日本の歴史や身分制度の影響を色濃く残した表現です。
「夢見るような結婚」の象徴ではありますが、そこには時代背景や女性の生き方の変化も垣間見えます。
何気なく使う言葉のルーツを知ると、言葉の重みや面白さも違って見えてきますね。
おまけ:言葉で遊ぶ
あなたにとっての「玉の輿」とは?
お金?地位?それとも愛情や安心感?
言葉の定義は、時代や人によって変わるもの。
ぜひ一度、自分なりの「玉の輿像」を考えてみるのも面白いかもしれません。

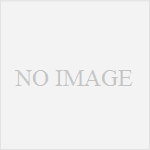
コメント